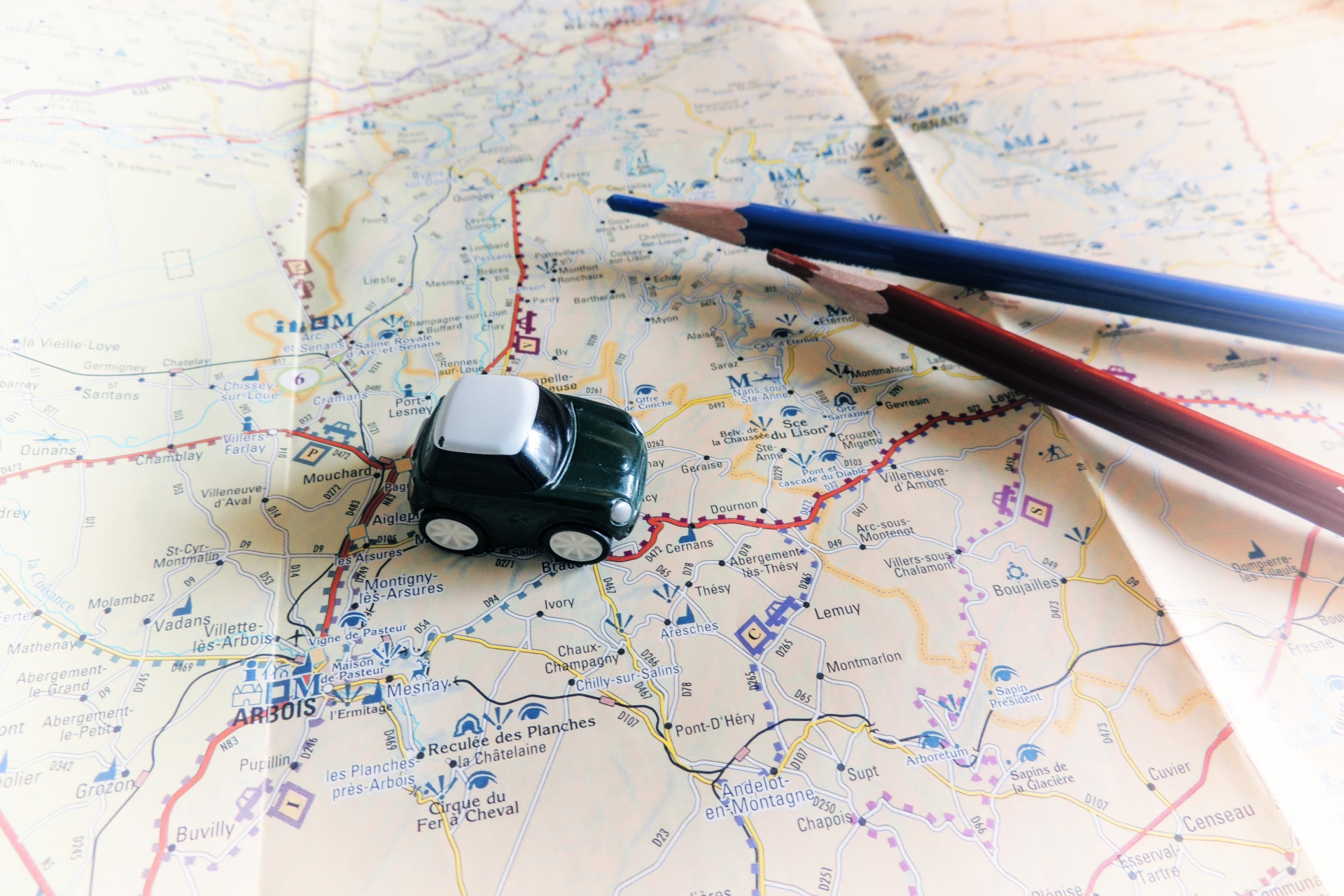マイクロバス免許の種類と取得方法|運転できる人数・車両総重量を解説
マイクロバスの運転に必要な免許の種類について悩んでいませんか? 今回は、マイクロバスを運転するために必要な「中型免許」について、車両総重量や乗車定員などの関係性から、取得方法、費用、よくある質問まで解説します。普通免許との違いや、教習所での取得方法、費用を抑えるためのポイントなども紹介します。マイクロバスを運転予定の方はぜひ最後までご覧ください。
1. マイクロバスを運転するために必要な免許の種類

結論から言うと、マイクロバスを運転するには中型免許が必要になります。”マイクロ”という表現で曖昧になってしまいがちですが、一般的には乗車定員11人以上29人以下の乗用車がマイクロバスと呼ばれます。
まずは一般的なマイクロバスの定義から紹介します。
1.1 マイクロバスの定義
一般的に言われるマイクロバスは下記のような条件の車両をいいます。このコラムでは、この定義に沿って解説していきます。
| 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 車両サイズ |
|---|---|---|---|
| 8,000kg未満 | 5,000kg未満 | 11人以上、29人以下 (補助席を含む) |
全長7m以内 |
以上がマイクロバスの定義となります。後ほど解説しますが、乗車定員11人以上。29人以下の車両を運転する場合には中型免許が必要となるため、マイクロバスを運転するには中型免許が必須となります。
1.2 中型免許がで運転できる車両
マイクロバスの運転には中型免許が必要と述べましたが、中型免許で運転することのできる車両の条件を下の表にまとめました。平成19年6月1日以前に普通免許を受けている人は「8t限定中型免許」を受けているものとみなされます。それぞれ運転できる車両が異なりますのでご注意ください。
| 免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|
| 中型免許 | 7,500kg以上、11,000kg未満 | 4,500kg以上、6,500kg未満 | 11人以上、29人以下 |
| 中型免許(8t限定) | 8,000kg未満 | 5,000kg未満 | 10人以下 |
2. 免許別車両総重量・最大積載量・乗車定員
マイクロバスを運転するために必要な免許の種類を理解するには、まず車両の区分について知っておく必要があります。
車両は車両総重量、最大積載量、乗車定員によって区分されます。それぞれの免許で運転できる車両の範囲を以下にまとめます。
| 免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|
| 普通免許 | 3,500kg未満 | 2,000kg未満 | 10人以下 |
| 準中型5t限定免許 | 5,000kg未満 | 3,000kg未満 | 10人以下 |
| 準中型免許 | 3,500lg以上、7,500kg未満 | 2,000kg以上、4,500kg未満 | 10人以下 |
| 中型8t限定免許 | 8,000kg未満 | 5,000kg未満 | 10人以下 |
| 中型免許 | 7,500kg以上、11,000kg未満 | 4,500kg以上、6,500kg未満 | 11人以上、29人以下 |
| 大型免許 | 11,000kg以上 | 6,500kg以上 | 30人以上 |
2.1 普通車の車両総重量・最大積載量・乗車定員
普通自動車免許で運転できる車両は、車両総重量が3,500kg未満、最大積載量が2,000kg未満、乗車定員が10人以下の車両です。一般的な乗用車や小型トラックなどが該当します。
2.2 準中型5t限定の車両総重量・最大積載量・乗車定員
準中型5t限定免許で運転できる車両は、車両総重量が5,000kg未満、最大積載量が3,000kg未満、乗車定員が10人以下の車両です。平成29年3月11日以前に普通免許を受けている人は「5t限定準中型免許」を受けているとみなされます。
2.3 準中型車の車両総重量・最大積載量・乗車定員
準中型自動車免許で運転できる車両は、車両総重量が3,500lg以上7,500kg未満、最大積載量が2,000kg以上4,500kg未満、乗車定員が10人以下の車両です。小規模な事業用トラックなどが該当します。
2.4 中型車8t限定の車両総重量・最大積載量・乗車定員
中型8t限定免許で運転できる車両は、車両総重量が8,000kg未満、最大積載量が5,000kg未満、乗車定員が10人以下の車両です。平成19年6月1日以前に普通免許を受けている人は「8t限定中型免許」を受けているとみなされます。
2.5 中型車の車両総重量・最大積載量・乗車定員
中型自動車免許で運転できる車両は、車両総重量が7,500kg以上11,000kg未満、最大積載量は4,500kg以上6,500kg未満、乗車定員は11人以上29人以下です。マイクロバスの多くはこの区分に該当します。
2.6 大型車の車両総重量・最大積載量・乗車定員
大型自動車免許で運転できる車両は、車両総重量が11,000kg以上の車両です。最大積載量は6,500kg以上、乗車定員は30人以上です。大型バスや大型トラックなどが該当します。
3. マイクロバスの概要

マイクロバスとは、一般的に車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員11人以上29人以下のものをいいます。。送迎バスや観光バス、コミュニティバスなど様々な用途で使用されています。車両の大きさや形状は様々ですが、大型バスと比較し、コンパクトな車体で小回りが利くことが特徴です。乗車人数が多いため、大人数の移動に適しています。
3.1 具体的なマイクロバスの車種
具体的なマイクロバスの例として、トヨタのコースターや日産のシビリアン、三菱ふそうのローザなどが挙げられます。これらの車両は、それぞれ異なる車両総重量、最大積載量、乗車定員を持っています。購入やリースを検討する際は、用途に合った車両を選ぶことが重要です。
マイクロバスの運転には中型免許が必要となります。中型免許の取得方法や費用については、この後詳しく解説します。
3.2 免許条件の注意点
特に注意が必要なのは中型8t限定免許をお持ちの方です。中型8t限定免許で運転できる車両の乗車定員は10人以下とされています。うっかりマイクロバスを運転してしまうと道路交通法違反となりますので注意が必要です。運転するバスの車両総重量、最大積載量、乗車定員は、車両の仕様書や車検証で確認できますので事前によく確認しましょう。
4. 中型免許の概要
中型免許は、車両総重量7,500kg以上11,000kg未満、最大積載量4,500kg以上6,500kg未満、乗車定員11人以上29人以下の車両を運転できる免許です。マイクロバスを運転するには、この中型免許が必要になります。 普通免許や中型8t限定免許ではマイクロバスを運転できないため注意が必要です。
4.1 受験資格
中型免許を取得するためには、いくつかの受験資格を満たす必要があります。
4.1.1 年齢
中型免許を取得できる年齢は20歳以上です。
4.1.2 運転経験
普通免許、準中型免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けていた期間が通算して2年以上の運転経験が必要。
年齢、運転経験が足りず受験資格を満たさない場合でも、19歳以上で運転経験が1年以上ある場合には「受験資格特例教習」を受講することで、受験資格を緩和することができます。
4.1.3 視力
両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上である必要があります。また、三棹(さんかん)法による深視力検査にも合格する必要があります。
視力や深視力については過去のコラムでも解説しています。
5. 中型免許の取得方法

中型免許を取得するには、主に以下の2つの方法があります。
5.1 指定自動車教習所に通う場合
ほとんどの方は、指定自動車教習所に通って取得します。教習所では技能教習と学科教習を受講し、修了検定と卒業検定に合格する必要があります。教習所を卒業後、運転免許試験場にて適正試験(視力・深視力検査)を受験し、合格すれば免許が書き換えられ中型自動車を運転することができるようになります。
教習所では、経験豊富な指導員から運転技術や交通ルールを学ぶことができ、計画的に教習を進めることができるため、初めて免許を取得する方や運転に自信がない方におすすめです。指定自動車教習所を卒業した場合、運転免許試験場での技能試験が免除されるため、効率的に免許を取得できます。
5.2 一発試験で取得する場合
運転免許試験場で、技能試験を受験して取得する方法です。教習所に通う必要がないため、費用を抑えることもねらえますが、試験の難易度が高く合格率も低いため、運転経験が豊富で自信のある方におすすめです。一発試験では、試験場ごとのコースの特徴などをあらかじめ把握しておく必要があります。
一発試験を受ける場合は、受験前に申請手続きが必要となります。詳しくは各都道府県の運転免許試験場のウェブサイトなどを確認してください。
| 取得方法 | メリット | デメリット | おすすめの人 |
|---|---|---|---|
| 教習所 | 計画的に教習を進められる 指導員から丁寧に指導を受けられる 運転免許試験場での技能試験が免除される |
費用が高い | 初めて免許を取得する人 確実に免許を取得したい人 運転に自信がない人 |
| 一発試験 | 早くに合格すれば費用と日数を抑えることができる | 合格率が低く、結果的に教習所に通う方が費用や日数を抑えられるケースが多い。 | 運転経験が豊富で自信のある人 |
6. 中型免許の教習概要(所持免許別)
中型免許の教習時間は、既に取得している免許の種類によって異なります。普通免許、準中型免許など、保有免許別に必要な教習時間数は以下のとおりです。
| 保有免許 | 技能教習 | 学科教習 | 最短取得日数 |
|---|---|---|---|
| 中型8t限定 | 5時限 | – | 最短4日 |
| 準中型免許 | 9時限 | 1時限 | 最短6日 |
| 準中型5t限定免許 | 11時限 | 1時限 | 最短6日 |
| 準中型5tAT限定免許 | 15時限 | 1時限 | 最短8日 |
| 普通免許 | 15時限 | 1時限 | 最短8日 |
| 普通AT限定免許 | 19時限 | 1時限 | 最短10日 |
上記はあくまでも目安です。個人の技能習熟度によって教習時限数は増減する可能性があります。また、教習所によっても多少の違いがあるため、詳しくは入校を希望する教習所に直接問い合わせるのが確実です。
7. 中型免許取得にかかる費用
中型免許を取得するには、教習費用や検定費用など、ある程度の費用がかかります。費用の内訳を把握し、予算を立てておくことが重要です。教習所によって費用は異なるため、複数の教習所で見積もりを取ることをおすすめします。
7.1 中型自動車免許取得にかかる費用
中型自動車免許を取得する場合、教習料金は、お持ちの免許や教習所、入校時期(繁忙期など)によって大きく変動します。一例として、普通免許所持者が中型免許を取得する場合、相場は25万円~30万円程度です。
この費用には、入学金、技能教習料金、検定料金などが含まれています。また、仮免試験受験手数料、仮免交付手数料などの諸費用も別途必要となります。教習料金以外にかかる費用として、教材費、写真代、交通費なども考慮に入れて総額を把握しておくと良いでしょう。
7.2 費用を抑えるためのポイント
中型免許取得にかかる費用を抑えるためには、いくつかのポイントがあります。まずは、複数の教習所の料金を比較検討することが重要です。キャンペーンや割引制度などを活用することも有効です。運転に自信のある方は、一発試験に挑戦するという方法もあります。一発試験は、教習所に通わずに試験場で直接受験する試験です。合格すれば教習費用を大幅に節約できますが、難易度が高いため十分な準備と練習が必要です。
8. マイクロバス免許に関するよくある質問

マイクロバスの免許に関するよくある質問をまとめました。疑問を解消して、スムーズに免許取得を目指しましょう。
8.1 中型8t限定免許でマイクロバスは運転できる?
中型8t限定では乗車定員10人以下の車両しか運転できないため、乗車定員11人以上のマイクロバスは運転することができません。キャンピングカー仕様などで乗車定員を10人以下に制限した場合でも、車両総重量が8,000kgを超えないか確認しましょう。超える場合には8tの限定解除が必要になります。
8.2 AT限定免許でマイクロバスは運転できる?
多くの場合運転することができません。マイクロバスを運転するには中型免許が必要です。この記事を書いている2025年10月時点では、中型免許にはAT限定免許がありません。したがって普通AT限定や準中型5tAT限定、中型8tAT限定免許をお持ちの場合でも、マイクロバスを運転することはできません。
8.3 マイクロバスの運転の注意点は?
マイクロバスは普通車よりも車体が大きく、乗車定員も多い車両です。そのため、運転には細心の注意が必要です。特に以下の点に注意しましょう。
- 内輪差:普通車に比べマイクロバスは内輪差が大きいため、カーブを曲がる際は、より内輪に注意して走行する必要があります。特に交差点での右左折時は注意が必要です。
- 外輪差:普通車と比べ右左折時に車両後方が大きく膨らみます。例えば左折時に車両後方は大きく右に膨らむため、右側にも注意が必要となります。
- 死角の確認:マイクロバスは死角が大きいため、こまめにミラーや目視で周囲の状況を確認する必要があります。特に、車線変更やバックの際は注意が必要です。
- 車両感覚:マイクロバスは車高が高いため、高さ制限のある場所を通行する際は注意が必要です。また、車幅も広いため、狭い道でのすれ違いや駐車には十分な注意が必要です。
- 乗客への配慮:マイクロバスは乗客を乗せて走行するため、急発進や急ブレーキは避け、スムーズな運転を心がける必要があります。また、乗客の安全を確保するため、シートベルトの着用を促すことも重要です。
その他、道路交通法を遵守し、安全運転を心がけることが大切です。
9. まとめ
繰り返しになりますが、マイクロバスを運転するには中型免許が必要です。普通免許や中型8t限定免許では運転することできません。
免許別の車両総重量、最大積載量、乗車定員は暗記するのも難しい部分です。お仕事などで座席の多い車や、車体の大きな車を運転する場合には、今一度車検証など見て、今お持ちの免許で運転することができるのか確認しましょう。条件違反や無免許運転に気づかない場合もあるため要注意です。
今回はたくさん数字の出る難しい内容でした。マイクロバスを運転する予定のある方はよく確認し、必要に応じて中型免許の取得を目指してみましょう。